この記事では、濡れた本をジップロックに入れて冷凍するのはなぜなのか?という疑問についてお伝えしていきます!
お気に入りの本にうっかりコーヒーをこぼしてしまった…そんな経験はありませんか?特に大切な本が濡れてしまった時、なんとか元通りにできないかと焦ってしまうものです。
そんな時に有効なのが、濡れた本をジップロックに入れて冷凍するという方法!
濡れた本を乾かす前に水分を凍らせることで紙の膨張や収縮を防ぎ、インクのにじみやカビの発生を抑えるというなかなか画期的なやり方なんです。
この時、濡れた本をジップロックに入れることで、冷凍庫内の乾燥やにおいうつりから本を守ったり、紙の劣化を最小限に抑える効果も期待できます。
なので、濡れた本を冷凍する時は必ずジップロックに入れてから凍らせるようにしましょう。
記事後半では、
など実践的な情報もたっぷり紹介しています!
大切な一冊を守るための知識として、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてくださいね^^
濡れた本をジップロックに入れて冷凍する理由についてさらに詳しく解説!

それでは早速、このやり方について詳しく解説していきますね^^
なぜ本を乾かす前に冷凍するのか
まず、濡れた本を乾かす前に冷凍するのは、本が受けるダメージをできるだけ抑えるためです。
水分を含んだまま自然乾燥させようとすると紙が膨張と収縮を繰り返してしまい、結果的に大きく波打ったり、インクがにじんだりする原因になります。
また、湿った状態が長く続くとカビが生えやすくなるという大きなリスクもあるんですね(´Д`。)
そこで冷凍することによって水分を一旦凍らせ、紙の中の水の動きを止めるわけです。これにより、紙の形状変化やインクの流出、カビの繁殖を一時的に食い止めることができるのです。
さらに、冷凍によって急速に劣化を防ぎながら、落ち着いて次の乾燥作業へと進む準備ができるというメリットもあります。
本のダメージを少なくするための「時間稼ぎ」と考えるとわかりやすいかもしれませんね!
ジップロックを使う理由と効果
では、なぜジップロックが必要なのでしょうか?
それは、本を冷凍庫内の乾燥やにおい移りから守り、さらに冷凍による紙の劣化を防ぐためです。
冷凍庫は非常に乾燥しやすい環境のため、濡れた本をそのまま入れてしまうと表面の水分が急激に蒸発してしまい、紙がガチガチに硬くなってしまうリスクがあります。
また、冷凍庫には肉や魚などの食材も入っていることが多いので、これら食材のにおいが本に移ってしまうことも珍しくありません。においうつりというやつですね。
ジップロックを使用することで、過度な乾燥から本を守り、ある程度におい移りも防ぐことができます。ただし、密封はしないので過信は禁物です!
このように、ジップロックを使うのは大切な本をできるだけ元の状態に近い形で復元するためにバリアのようなものなんですね(´・∀・)ノ゚
濡れた本を冷凍して復活させる正しい手順を解説!
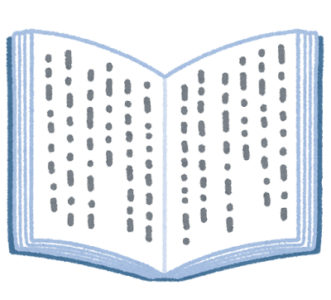
本をきれいに復活させるためには事前の準備がとても大切です。準備不足のまま作業を始めてしまうと、かえって本を傷めてしまうことにもなりかねません。
スムーズに進めるためにも、必要なものを事前にしっかり揃えておくことが成功のカギです。
これからご紹介するアイテムをきちんと準備して、落ち着いて作業を進めていきましょう^^
準備するもの
応急処置から修復作業までの流れ
まずは、全体の流れを確認しておきましょう。
工程はそれほど多くないので、ひとつずつ確実にこなしていってくださいね!
- 手順①:濡れた本の表面の水分をタオルやキッチンペーパーで軽く押さえて拭き取る
- 手順②:ジップロックに入れて口を少し開けた状態で冷凍庫に立てかけて一晩凍らせる
- 手順③:凍った本を袋から取り出し、重石を乗せて約5日間自然乾燥させる
- 手順④:乾燥中は時々重石を外してページに風を通すようにする
- 手順⑤:必要に応じてコピー用紙を挟み、数時間おきに取り替えながらさらに乾燥を促す
それでは、詳しく見ていきましょう^^
まずは、慌てずに濡れた本の表面の水分を清潔なタオルやキッチンペーパーでやさしく拭き取ります。この時、こすらずポンポンと軽く押さえるようにすると紙を傷めにくくなります。
焦って擦ってしまうと表面が破れたり剥がれてしまうことがあるので力加減にはご注意ください!
次に、ジップロックなどの「密閉できる袋」に本を入れます。
ただし、袋の口は完全には閉じずに少しだけ開けた状態で冷凍庫に立てかけて入れましょう。このまま一晩(12時間以上)放置し、本をしっかりカチコチに凍らせます。
凍った本を袋から取り出したら、平らな場所に置き、その上に重石をそっと乗せます。
本の上に板や厚めの本を置き、その上から均等に重みをかけるとよいでしょう。この状態で5日ほど自然乾燥させればOKです(*・∀-)☆
さらにきれいに乾かすためのコツとしては、乾燥中に時々重石を外し、ページを少しめくって風を通すと乾きが早まりカビ防止にもなります。
また、より速く乾燥させたい場合はコピー用紙など白い紙をページの間に挟む方法もおすすめです。
色付きや印字された紙は色移りの原因になるので間違っても使わないようにしましょう。コピー用紙は数時間おきに新しいものに取り替えるとより効果的に水分を吸収してくれますよ♪
これくらい丁寧に作業していけば、完璧とまではいかずともかなりきれいな状態で復活させることができるはずです^^
冷凍庫での保管時間と注意点
濡れた本を冷凍庫に入れる時間は、最低でも12時間以上を目安にしましょう。
これは、本の内部までしっかりと凍らせることで紙の繊維内に残った水分が安定し、紙の変形やシワを防ぐためです。
凍結が不十分だと乾燥時に紙が伸縮してしまい、結果として波打ったり、ひどい場合には破れたりすることもあるので注意が必要です。
冷凍中の注意点としては、まず本をジップロックなどの袋に入れた状態で立てて冷凍庫に置くことです。寝かせて置くと自重で本がゆがむ可能性があるので注意が必要です。
また、袋の口は軽く閉じる程度にとどめ完全密閉にはしないようにします。完全に封をしてしまうと、内部に湿気がこもり凍る前にカビが発生するリスクがあるからです。
さらに、冷凍庫の中で他の食材と直接触れないように配置することも大切です。特に生鮮食品のにおいが移ってしまう恐れがあるため、においのある食材からは少し離しておくとなお安心です。
あと、冷凍庫に入れっぱなしにするのも避けましょう。
数週間以上放置すると冷凍庫内の乾燥が進みすぎ、本が極端にパリパリになって紙が脆くなってしまう危険性があります。
冷凍庫から出した後に気をつけることについて
冷凍した本を取り出したあとは、いきなり袋を開けるのではなくまず常温で30分ほど置いて温度差を和らげましょう。急な温度変化による結露を防ぐための大切なステップです!
その後、ページ同士がくっつかないよう、ゆっくりと慎重に少しずつめくりながら乾燥させていきます。
無理に開こうとすると、破れたりインクが移ったりするリスクがあるのでやさしく扱うことが重要です。
乾かす際には新聞紙や吸水性の高い紙をページの間に挟んで自然乾燥させましょう。この時、吸水紙はこまめに交換することでよりきれいに仕上がります。
また、カビを防ぐためにはできるだけ早く乾燥作業を終えることがカギとなります。
風通しの良い場所で乾燥させ、必要に応じて除湿機や扇風機の弱風を活用するのも効果的です。
丁寧なケアを続けることで大切な本をより美しく復活させることができますよ(*・∀-)☆
冷凍する以外で濡れた本を復活させられる方法はある?

実は、冷凍以外にも「吸水シート」や「乾燥剤」を使って水分を取る方法があります。
軽い濡れの場合は、まずタオルや新聞紙で本の表面とページの間の水分をやさしく吸い取ることが基本です。
この時、強く押し付けず軽く押さえる程度にすることで紙へのダメージを防ぐことができますよ!
その後、扇風機の弱風を当てながら自然乾燥させると比較的きれいな状態で復旧できる可能性が高くなります。
乾かす際には本を立てかけるのではなく、なるべく平らな場所に広げ、ページ同士がくっつかないように注意してくださいね。
さらに乾燥を早めたい場合は、市販の乾燥剤や吸水シートを本の周囲に置いて湿気を取り除く方法も有効です。
ただし、乾燥剤が直接本に触れないように薄い紙でカバーをするなどの工夫をするとより安心です。
ちなみに、
ような場合には、こうした自然乾燥だけでは紙の波打ちやカビのリスクを完全に防ぎきれません。
そのため、広範囲に濡れてしまった場合はやはり冷凍してから慎重に乾燥させる方法をおすすめします(´・∀・)ノ゚
濡れた本の復活に関するよくある質問(FAQ)

最後に、今回の内容に関係のある質問について補足しておきますね!
Q:冷凍庫に入れるタイミングは?
濡れた本を復活させるのであれば、できるだけ早い方が良いですね!
放置していると紙が水分を吸ったまま劣化が進み、カビが生えやすくなってしまいます。そのため、応急処置が終わったらできるだけ速やかに冷凍庫へ入れるのがおすすめです!
早めに冷凍することで水分が凍結して劣化の進行を一時的に止めることができ、本へのダメージを最小限に抑えることが可能になります。
ちょっとしたタイミングの違いが仕上がりに大きく影響してきますので、スピードを意識して行動しましょう!
Q:全ページびしょ濡れの場合はどうする?
全ページが濡れている場合でも、基本的には同じ手順で冷凍して問題ありません。
冷凍することで水分の移動を一旦止め、紙の変形やカビのリスクを抑えることができるからです!
ただし、乾燥作業にはかなり時間がかかることを覚悟しておきましょう。
凍結した本を取り出した後は、重石を乗せてゆっくりと自然乾燥させる必要があります。 乾燥の途中でもこまめにページをめくり、空気を通してあげると早くきれいに仕上がります。
焦らず、じっくりと時間をかけて進めることがポイントです^^
Q:自然乾燥と冷凍乾燥の違いは?
自然乾燥はどうしても紙が波打ったり、インクがにじんだりするリスクが高くなります。特に、本全体が濡れている場合や、湿気が強い環境では乾燥ムラやカビの発生も心配されます。
一方で、冷凍乾燥は水分を一旦凍らせることで紙の繊維の動きを抑え、波打ちやインクにじみを最小限に食い止めることができます。
そのため、大切な本や思い出の詰まった本ほど、冷凍を取り入れた丁寧な復活作業を行うことが強くおすすめされます。
Q:カビの発生を防ぐには?
やはり乾燥までのスピードがカギになります!
濡れたままの状態が長時間続くと紙にカビが発生しやすくなり、取り返しのつかないダメージにつながってしまいます。
そのため、濡れた本は放置せずできるだけ早い段階からこまめに乾燥を促すことがとても大切です。
本の状態を見ながら、適度にページを開いたり風を通したりして、乾燥の進み具合をチェックするのを意識してくださいね!
Q:すでに波打ってしまった本も復活する?
乾燥が進む前に冷凍しておけば紙の波打ちをかなり抑えることができますが、すでに波打ってしまった場合では仕上がりが悪くなってしまうかもしれません。
ただし、完全ではないものの改善する余地はあるので試してみるのは全然アリです!
重しを使って数日間しっかりと平らに乾燥させることである程度はページを整えることが可能です。
また、乾燥中に適度にページをめくり風を通す作業を丁寧に続けることで、紙のクセをやわらげる効果も期待できます。
ただし、一度強く波打ってしまった紙を完全に元の新品同様に戻すのは難しいので、できるだけ早めの対処を意識してくださいね!
まとめ:大切な本を守るためにできること
本が濡れてしまった時は、まずは焦らず落ち着いて応急処置を行いましょう。
そのままにしてしまうと紙の波打ちやカビの発生が進み、取り返しのつかないダメージを受ける恐れがあります!
応急処置をしたあとは、必ずジップロックに入れて冷凍することがポイントです。
冷凍することで水分を一旦凍結させ、紙の繊維の変形やインクのにじみを防ぎながら劣化の進行をストップさせることができます。
少し手間と時間はかかりますが、その丁寧な対応こそが、大切な一冊をできるだけ美しい状態で復活させる近道になります。
いざという時に落ち着いて対処できるよう、今回ご紹介した内容を参考にして本を守る準備をしておきましょう!
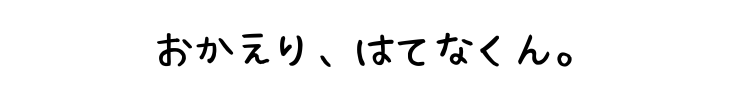
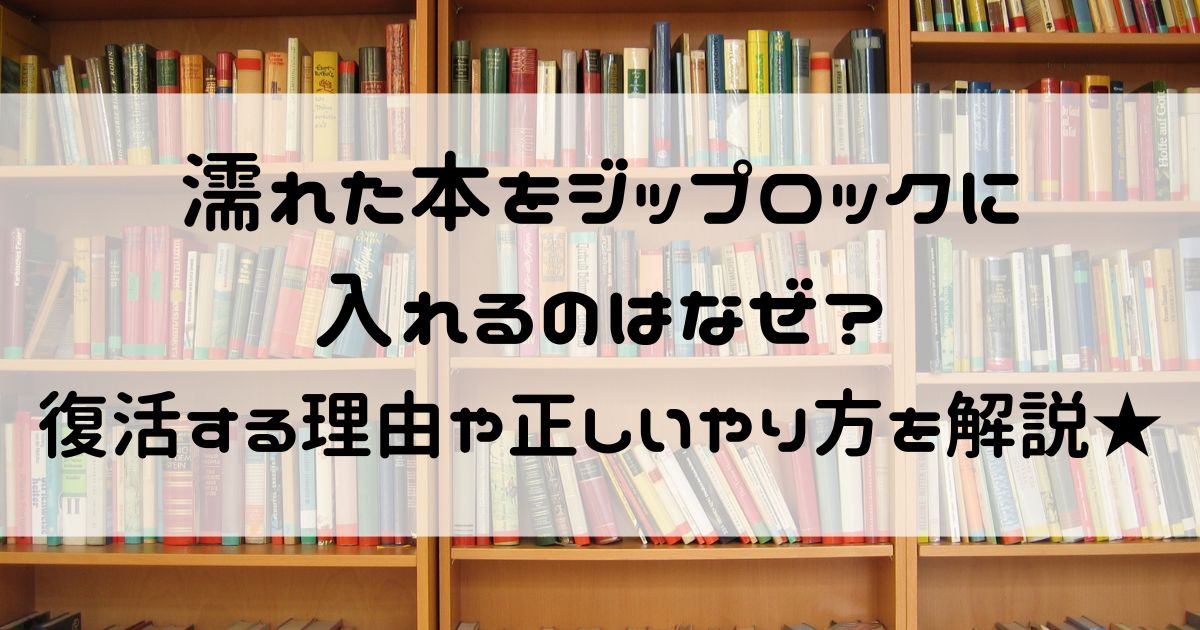
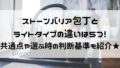
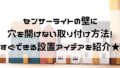
コメント